私たちは「意識」によって世界を認識しています。あなたの目の前にあるスマホであれ、パソコンであれ、脳の中では感覚器官から送られてきた電気信号(活動電位)でしかありません。そのような入力信号に意味を与え、モノとして認識できるのは「意識」と呼ばれるもののおかげではないでしょうか。
私たちに「意識」が備わっていると感じられるのは、それを失うことがあるからでしょう。まるで、髪をバッサリ切った後になって、かつて生えていた髪の存在に気づくように。眠りに落ちる瞬間、麻酔薬が効いた瞬間、私たちは「意識」というものが存在していたことに逆説的に実感するのです。
「意識」は神出鬼没?「意識」は自己生成的?
ヒトに限らず、地球上に存在する生物の多くは睡眠をとることが知られています。ヒトは眠っているとき夢を見ることもあれば、夢を見ることなく「意識」を失うこともあります。このような経験から「意識」に関してどのようなことがわかるでしょうか?
まず「意識」は消失するのだということ。私たちは、生きている限り、常に世界に対する「目」を持ち続けていると錯覚してしまいます。ですが、たとえば交通事故で大きな衝撃を受けたときや外科手術で麻酔薬を投与されたときなど、世界を認識する「主観的な経験」は容易に消え去ってしまうのです。
意識を失った他人を客観的に見ることはできても、意識を失ったあなた自身を主観的に経験することはできません。そのため「自分が意識を失うことはない」「自分は死ぬことはない」と誤解してしまいます。しかし、誰もが意識を失い、やがて死んでいくのです。この主観的な経験が消えてしまった世界では、「わたし」「世界」という感覚は消え去り「無」のみが広がるのでしょうか?
次に、外的世界から刺激されなくても「意識」は生まれるということ。目覚めているときとは異なり、眠っているときは五感(視覚・嗅覚・聴覚・触覚・味覚)による感覚入力を積極的に求めて行動することはありません。それにも関わらず、夢を見ているときに、起きているときと同じような出来事や、非現実的な事件を経験するはずです。つまり、私たちの脳で「意識」がはたらくには、感覚器官による入力情報は必ずしも必要ではなく、脳の内的な活動だけで事足りるといういうわけです。
「意識」の実態を明らかにする経験サンプリング
私には「意識」があり、他人にも「意識」がある。この「意識」という主観的な経験の内容はどのようにして調べられるのでしょうか?
「意識」の内容を調べる方法として容易に思いつくのは、内的な世界で経験したことを説明してもらうという方法です。
突然ですが、今あなたは何を考えていますか?
- えっ、別に何も
- さっき食べたご飯のこと
このような質問に対する答えが、あなたの「意識」の内容そのものだということです。現象は複雑なはずなのに、その観測方法は非常に単純に見えます。これで本当に主観的な経験をとらえたことになるのでしょうか。「意識」によって内的な世界を経験することと、その内容を想起して言葉で説明することの間には大きなギャップがあるように感じられます。
さて、このように経験した内容を説明することで「意識」の内実を明らかにする方法は、経験サンプリング(Experience sampling)と呼ばれます。覚醒中とか睡眠中といった活動レベルは関係なく、「今、何を感じていたか」を問うことで、「意識」のレベルや経験内容を調べるのである。
たとえ起きていても「意識」が明晰だとは限らない。退屈な授業を受けたり講演を聞いたりして、ボーッとしてしまった経験は誰にでもあるはず。このとき、強面教師(あるいは熱血講演者)に「君、意識飛んどるぞ!」と言われたのではないだろうか?
逆に、寝ていても夢を見ていて「意識」が明晰なときもある。夢の中で、空を飛んでみたり、憧れの有名人に会ってみたり、「仮想」トイレに行きそこでトイレを…。
「意識」は常に変動するもの!
私たちの活動レベルは「覚醒(wakefulness)」と「睡眠(sleep)」に大別されます。さらに、「睡眠」はレム(rapid eye movement: REM)睡眠とノンレム(non-rapid eye movement: NREM)睡眠に分類されます。これは、ポリソムノグラフィー(Polysomnography: PSG)と呼ばれる手法で測定した脳波(Electroencephalogram: EEG)・眼球運動(eye movement)・筋電図(muscle tone)などに基づいて細分化されます。
睡眠中の「意識」について、レム睡眠中に起こされた人の大部分は夢で経験した内容を明確に説明できる一方で、ノンレム睡眠中に起こされた人は夢の内容をハッキリと思い出せないという傾向があります。そのため、レム睡眠は「夢見睡眠(dreaming sleep)」と形容されることがあります。
しかし、ノンレム睡眠中だからといって夢を見ないわけではなく、レム睡眠中と比較して穏やかで展開の少ない夢を見ることが最近の研究で明らかにされています。レム睡眠とノンレム睡眠で程度の差こそあれ、睡眠中でも「意識」は現れたり消えたりしているのです。
…
あっ、ボーッとして意識が飛びそうでした。
ちなみに、筆者は小学生のころボーッとすることが多くて「ボーちゃん」で呼ばれていました。
別に鼻は垂らしていなかったですけど! (余談です)
このように見てくると、「覚醒=意識オン」であるが「睡眠=意識オフ」という関係性は疑わしいといえます。
起きているにしても、入社試験で面接を受けているときのように意識レベルが高い(緊張のあまり意識を失いかけた方もいらっしゃるかもしれませんが)こともあれば、ソファーでくつろいで今にでも寝てしまいそうなときのように意識レベルが低くなることもあります。
一方で、ベッドの中で眠っていても常に意識がないわけではなく、現実世界とは異なる世界線で突飛な経験をする意識レベルになることもあります。
ということは、私たちの「意識」のレベルは「低」から「高」の間を行ったり来たりしているようなものなのかもしれません。たしかに「意識」のレベルは体内のリズムや外界の刺激に影響を受けることでしょう。ですが、それは「スイッチ」のように2進数で表現しきれるものではなく、常時連続的に変化するものだといえそうです。
このような「意識」レベルの連続性を定量化する方法や、それを実現する脳の仕組みが気になってきますね。
何かコメントをいただけるとありがたいです!
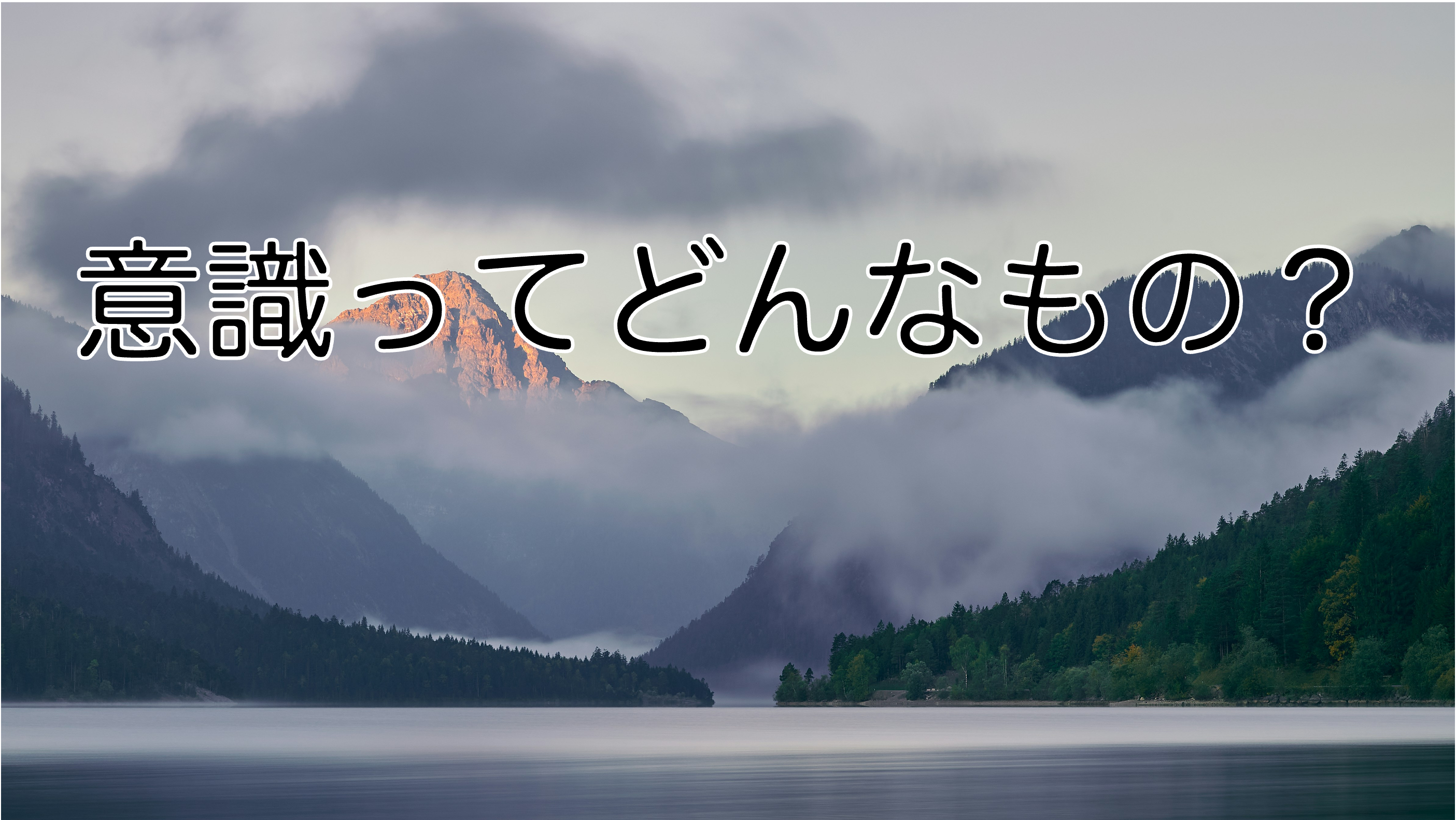


コメント