この記事では、東大の情報系大学院で学びたいという方に大学院入試合格のための戦略をお伝えします。私は、東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻で研究しています。元々は工学部計数工学科システム情報学専攻に所属していたので、大学院入試に関しては有利だったと感じる側面が多くあります。このような情報格差を是正するために、学部生の頃に東大に所属していなかったという方にも、どのように大学院入試に向けて準備し対策すれば良いのかを徹底的に解説します。
東大生は有利か
「結局、内部生の方が有利なんでしょ」と諦めてしまうのはもったいないです。大学側から正式な合格率が公表されているかは定かではありませんが、学生目線からして内部生の合格率は全体の合格率よりも高いと個人的には感じます。それは東大生のほうが優秀だというわけではなくて、内部生と外部生の間の情報格差がひとつの要因だと思います。内部生は豊富な過去問にアクセスできたり、研究室の先生や先輩との交流も容易であったりして、大学院入試への対策がしやすい環境が整えられています。一方で、外部の大学から受験する場合は、そのような情報や人脈にアクセスできないという現状があるのではないでしょうか。
情報にアクセスしやすいという意味で、東大生のほうが有利だと考えることもできます。しかし、内部生だけでなく外部生の方も徹底的に対策すれば、必ず合格できると考えています。ですので、内部生として大学院入試を経験した立場から、大学院入学を志す全ての方に向けて、対策方法を紹介します。
何に注力するべきか
システム情報学専攻の大学院入試対策として注力するべきことは圧倒的に試験対策です。
大学院入試は研究計画書や面接が重要だという印象もありますが、試験の結果が大きな比重を占めると考えて良いでしょう。これは試験準備に要する労力の方が圧倒的に必要だからです。
試験は、TOEFL・共通数学・専門分野の3種類があります。TOEFLは外部試験ですから、各受験者がそれぞれ受験して試験結果のデータを提出します(大学側から試験援助などはありません)。一方、共通数学や専門分野は大学独自の試験で、いわゆる大学入試と同じように受験します。
試験日までに行うこと
具体的にどのような対策を行うか。
それを考える前に、まずは敵を知ることが重要です。この記事を読んだら、すぐに大学院のWebページにアクセスして募集要項を熟読することを忘れないでください(募集要項の味気なさにうんざりして、この記事に辿り着いたのかもしれませんが…)。
では、改めて具体的にどのような対策を行うかを解説します。
徹底的に過去問対策をすること
試験を受験した立場からすると、研究計画書や面接の点数よりも試験の点数が圧倒的に重視されていると感じました。
特に専門分野の問題は重要です。過去5年分の問題は公開されていますので、それらを眺めたり解いたりして傾向を掴みましょう。
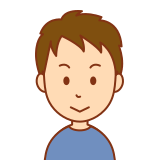
過去問を見て敵を知りましょう!
近年では出題範囲が、信号処理・電子回路・制御理論に限定され、それらの分野から2問を解くという形式です。
僕は信号処理と制御理論を選択すると決心しており、電子回路への対策は行いませんでした。(信号処理と制御理論で失敗したらまさに撃沈していたということですね)皆さんがどのように選択するかは自由ですが、自分の好みに応じて、あるいは将来的に使うことが予想される分野に近い問題を選択するのが良いのではないでしょうか。
外部生もできればやりたいこと
公開されている過去問に対して、内部生には過去問の蓄積があります。ですから、外部生の方もそのような過去問にアクセスすることが圧倒的に有利だと思います。
では、内部生とのネットワークをどのように作るかということですが、人脈があったりSNSでの交流があったりすれば良いですが、唯一の絶対的な方法としては、5月中旬に開催される専攻別説明会に参加することだろうと思います。
ハイブリット開催かと思いますが、できれば対面で参加することが望ましいでしょう。そこでは、全体的な専攻に関するよくある説明がなされた後、各研究室ごとに分かれて質問や相談ができます。
教員の先生方や学生も参加しているため、その場で様々な質問ができます。他県からの参加は難しいということがあるかもしれませんが、できれば参加して雰囲気を掴むことが重要だと思います。
一部の内部生も参加しているはずですので、そこで内部生との人脈をつくるしかないかもしれません。その交流で、過去問を共有したり一緒に勉強したりする仲になれるかはわかりませんが…。
いずれにせよ、外部生の方で、専門分野に対する不安があるようでしたら、何とかして内部生に交流をつくり実際に問題を共有してもらったり、少しでも内容を教えてもらうことができれば良いだろうとは思いますね。
過去問だけでは足りない
受験勉強でもそうでしたが、過去問だけ解いても傾向が掴めるだけであって、それが本番の試験に役立つとは限りません。同じ問題は出題されませんから。ですから、当然過去問以外の対策をしたいところです。ですが、内部生は主に3年生の間に受講してきた講義の知識がありますので、それを思い出したり復習すれば対応できるという面もあります。
基本的に、計数工学科システム情報学コースでは、信号処理論第一・第二、回路学第一・第二、制御論第一・第二を受講してそれぞれの分野の基礎を学びます。教科書通りに進む講義というよりも、教員の方が作成した(あるいは伝統的に継承されてきた)スライドをもとに抗議が進んでいくという形式でした。まあ、よくある大学の講義の形態かと思います。
その中でも信号処理論に関しては、別に参考書を指定されることもあまりなかったように記憶しておりますので、何か好きな本を選んで勉強されれば良いのかと思います。基本的な連続時間信号や離散時間信号に対する理解があれば、十分ではないでしょうか。
回路学は特に対策していないので、特に共有できることもありませんが、回路学の初回の授業で紹介された本を共有しておきますね。
制御論は圧倒的にこれですね。僕の時代は著者の先生がいらっしゃったので尚更その傾向が強かったです。この本の内容を全体的に理解しておけば十分だと思います。少し説明でわかりにくいところがあれば最近出版された本などを参照して理解を深めることでしょう。
これといった新しいことは述べていませんが、専門分野の傾向を掴んだ上で、基礎的な内容を把握しておけば絶対に対応できます。特に内部生は演習の時間で、それぞれの分野に近い問題を解いていることもありますから、そのような対策を行なっておきましょう。
TOEFL対策・受験を忘れないこと
普段からTOEFL対策を行なっている人はおそらく少数で、大学院入試で求められるために受験するという人も多数でしょう。試験対策は試験が行われる8月までに延長はできるわけですが、TOEFLは出願時に点数の提出が求められるため、随分と早い時期から対策を行う必要があります。僕の場合は、春休みの2月ごろから対策を始めて、5月に一度だけ受験しました。
僕の失敗としては、受験登録が遅すぎたために近くの会場で受けられず埼玉の会場まで行かないといけなくなりました。たしか5月祭のあたりに受験しました。自宅受験をすると集中できないかと思い、会場受験すると決断していましたが、まさか直前になると近くの会場が埋まっているとは想定していませんでした。
どうせ受験することになるのですから、大学院への入学を決めたら早めに受験申し込みを行い会場を押さえてしまうことが大切だろうかと思います。目標日を設定すれば、目標が明確になっていいでしょうしね。後は、一度だけでは不安だろうという人もいると思いますから、春休みなどの時間があるときに集中して対策して、早めに受験しておくというのも手かと思います。内部生の様子を見ていても、4月や5月に受けるという人が多いようでしたから、それほど焦る必要もないかと思いますが、納得のいくような対策をしたいところですね。
点数については正直わかりません。高ければ高い方が望ましいというところでしょうが、ボーダーはあるものなのですかね。上は100点越えの方もいるようですし、下は50点付近の人もいるようです。80点とか90点くらいあれば平均的なのではないでしょうか。ちなみに大学院に入学すれば英語を使う機会も増えると思いますので、大学院入試で鍛えておくのも一つの手かと思います。
研究室訪問を行うこと
東大生は3年生のうちは研究室ごとの実験を行う期間と、4年生のうちはそれぞれの研究室に所属して実験(ミニ卒論)を行うという計画になっています。修士課程への進学を希望していたり、興味のある研究室での実験を行うこともできるため、その雰囲気を知ることができます。ですので、教員の方とのアクセスも行いやすい環境があります。また、4年生の実験配属では、研究室にもよると思いますが歓迎会のようなものが催されて、先輩や教員とフランクな会話を行うことができるため、そこで研究や進学に対する相談もできます。
また、内部生は確か5月だったと思いますが、卒論説明会という名目で実際には大学院説明会があります。食事付きで行われます。いわゆる外部向けの選考別説明会を内部で行うといった感じでしょうか。そこでは、さらにフランクに成就人への質問もできます。そのように研究や進路に関して相談する機会に恵まれています。ですから、外部生の方はまずは選考別説明会に参加して、先輩や教員の方に研究や生活面での質問をしてみることがおすすめです。あるいは、興味がある研究室のホームページをググってみたり、特に大学教員はメールアドレスを公開していることが多いですから、その先生にメールでアプローチしてみることが得策でしょう。
まとめ
内部生は圧倒的に有利な立場にあります。それは豊富な過去問にアクセスしたり、先輩や教員への質問がしやすい環境が整っているからです。また学部時代のカリキュラムで学んでいれば、大学院入試に必要な知識が身につきやすいこともあると思います。つまり、今までの定期試験や演習問題の延長として捉えられるということです。
そのような中でも対策するべきこととしては、まずは早めに対策を始めてまず敵を知りましょう。そして、徹底的に対策することを優先しましょう。そのためのマイルストーンとしては、
まず過去問を見て傾向と対策を知ること、数学分野と専門分野の対策を始めることが挙げられます。基本的な参考書を読んで、基礎的な知識を身につけることが明確に必要です。その上で、内部生や先輩と交流をできれば過去問に関する情報をゲットできればなお有利になることでしょう。
その上で、英語試験対策を早めに行うことです。春休みを過ぎれば4年生の生活で忙しくなることも考えられますから、遅くとも春休みのうちにしっかりと対策を行い、提出期限にまで余裕をもって目標点を獲得しておくことでしょう。
第3に研究室の環境を知っておくということでしょう。入試対策という意味では、研究室との先生とのコミュニケーションが重要だとは言えないような気がします。たしかに志願理由書に研究内容に関する記述を記す部分もあるが、基本的には試験の点数ベースという印象がある。また面接も3分間もかからなかった印象である。質問された内容も一つだけであり、内容も最もベターなもの(志望理由)でした。ですので、試験対策をすることが先決ですが、研究室の活動や生活を知った上で出願するべきでしょう。
そのためにも、外部生は特に直接アプローチしてみることか、5月中旬に開催される専攻別説明会に参加して、実際に研究室を訪問させてもらったり、先輩の話を聞いてみたりすることが現実的であり、参考になることでしょう。

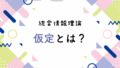

コメント